\タイムセール開催中/
登山ギア・スマートウォッチ・アクションカメラなど最大50%オフ!
Amazonを確認する▶

スマホの写真では物足りない
アクションカメラの広角映像から表現の幅を広げたい
背景ボケやズームの景色も撮影したい
登山の思い出を表現豊かに残したいなら「ミラーレス一眼カメラ」はおすすめの選択肢です。
本記事では、アクションカメラを6年間使ってきた筆者が、より表現の幅を広げたいとの思いから、本気で一眼カメラを選ぶ際に行った検討事項を徹底的にまとめました。
高価なミラーレス一眼カメラやレンズの選び方や登山での携行方法など必要事項をまとめています。



結論、ミラーレス一眼カメラのSONY α7 IIを選びました
登山におすすめのミラーレス一眼カメラ
| ブランド 写真 | 登山 おすすめ度 | 特徴 | 参考価格 (税込) | ページ内 詳細へ移動 | センサーサイズ | 有効画素数 | マウント形状 | ボディ内手ブレ補正 | バッテリー性能 | 可動式モニター | 操作性 | 動画性能 | 耐久性 | 重さ |
(5.0 / 5.0) | フルサイズ 高性能ながら小型サイズ グリップが浅く操作性やや低め | 252,000円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約3300万画素 | ソニーE | 最大7.0段 | 約530枚 | バリアングル式 | グリップが小さめ ボタンが少なめ | 4K60p | 0~40℃ | 約514g | |
(4.5 / 5.0) | 信頼と安定の高機能モデル やや重たく、携帯性に欠ける | 289,438円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約3300万画素 | ソニーE | 最大5.5段 | 約520枚 | バリアングル式 | 握りやすいグリップ ボタンが豊富 | 4K60p | 0~40℃ | 約658g | |
(4.0 / 5.0) | AFや手ぶれ補正人物撮影に強み 重ため、画素数は控えめ | 29,6989円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約2420万画素 | キャノンEF | 最大8.0段 | 約450枚 | バリアングル式 | 握りやすいグリップ ボタンが豊富 | 4K 60p フルHD 180p | 0~40℃ | 約670g | |
OM SYSTEM OM-5 Mark II | (3.5 / 5.0) | 圧倒的な軽さと耐久性を実現 フルサイズより画質は劣る | 162,800円 | 詳細を見る | マイクロ フォーサーズ | 約2037万画素 | マイクロフォーサーズ | 最大6.5段 | 約310枚 | 3.0型2軸 可動式液晶 | グリップは小さめ ボタンが少ない | C4K:24p 4K:30p FHD:60p | -10~40℃ | 約414g |
登山でより美しい景色を写真や映像に残したい方は、ぜひ最後まで読んでください。
登山で「ミラーレス一眼」が選ばれる理由


「一眼カメラ」と聞くと、一眼レフを連想する方が多くいますが、ミラーレス一眼は一眼レフより軽量で高性能なモデルが多数ラインナップされ、登山用カメラの主流になっています。
一眼レフとミラーレス一眼の違い
| ミラーレス一眼 | 一眼レフ |
|---|---|
| 本体の鏡をなくし、センサーが捉えた映像を電子ビューワインダーに表示する構造 軽量 コンパクトモデルが多い 各社の競争が激しく新機能開発に期待 | 内部に鏡(レフ)があり、昔ながらの光学ファインダーを覗く構造 昔ながらの構造にこだわりがある人におすすめ 大きくて重たい 大手企業の撤退が目立ち、技術革新は乏しい |
もちろん、一眼カメラでなくても、アクションカメラやスマートフォンでもきれいな映像や写真は残せますが、撮影できる写真や動画の性質は大きく異なります。
登山におすすめのカメラ 性質比較
| ミラーレス一眼 | 一眼レフ | アクションカメラ | スマホ | |
|---|---|---|---|---|
| 携帯性 | やや軽め やや小さめ | 重たい 大きい | 軽量 コンパクト | 軽量 コンパクト |
| 画質 | かなり高い | かなり高い | 高い | 高い |
| 動画性能 | 高い 表現幅が広い | 低い | 高い 広角 or 360度 | 少なめ |
| 表現力 | 豊富 | 豊富 | 広角メイン | 普通 |
| 技術の進化 | かなり高い | 低い | かなり高い | かなり高い |
| 登山への おすすめ度 | 高い こだわる人向け | 低い | 高い 初心者向け | 高い モデルにより異なる |
ミラーレス一眼は、望遠や接写、ボケ感のある映像など、アクションカメラやスマホで表現できない映像の幅を広げられます。



登山におすすめのカメラ機材について、下記でまとめていますので、合わせてご覧ください👇️
【登山初心者におすすめ】動画撮影できるカメラ機材


>> 目次に戻る⇑
登山向けミラーレスカメラの選び方 8選


画質とセンサーサイズ【表現力】
ミラーレス一眼を選ぶ際に最も重要な点が、写真の画質を左右する「センサーサイズ」です。
センサーサイズは、レンズが捉えた光を記録するカメラの画質を決定し、サイズが大きくなるほどカメラやレンズのサイズも大きく、重くなります。
主流センサーサイズと特徴の比較
| センサーサイズ | フルサイズ | APS-C | マイクロフォーサーズ |
|---|---|---|---|
| ひと言でいうと | 画質の王様 | バランス型 | 機動性重視 |
| 画質 | とても高い | 普通 | やや劣る |
| 画角 | 広い | 普通 | 狭い |
| 暗い場所での強さ (星空・朝夕など) | とても強い | 普通 | やや苦手 |
| 背景のボケ | とても得意 | 普通 | やや苦手 |
| カメラサイズと重さ | 大きい | 普通 | 小さい |
| レンズの大きさ | 大きい | 中間 | 小さく!・軽い |
| 価格 | 高価 | 中価格帯 | やや低め |
| こんな人におすすめ | 画質に妥協したくない 星空撮影したい ご来光も狙いたい 光の演出を楽しみたい | 画質と携帯性の バランス重視 予算を抑えたい | 軽量は外せない 耐久性も重視したい 予算を抑えたい |
画質と携帯性のバランスを求めるなら「APS-C」という選択肢もありますが、最高の写真や動画を追求するならやはり「フルサイズ」がおすすめです。
ミラーレス一眼カメラにハマる方は、最終的に画質を求めてフルサイズに買い替える方が多く、結果的に買い替え時にレンズの互換性がなくてコストがかかります。



初心者でも本気でカメラに挑戦したいなら、撮影幅が広がるフルサイズをおすすめしますよ
レンズによる拡張性【将来性】


カメラはレンズとセットで初めて真価を発揮するため、登山向きの軽量・コンパクトなレンズが充実している「レンズマウント(規格)」を選ぶことが非常に重要です。
カメラを選ぶ際は、ボディだけでなく、使いたいレンズを含めた総重量と価格で判断するのが後悔しないための鍵です。
主要なミラーレス一眼のレンズマウント
| マウント形状 | 対応センサー | 特徴 | 主なブランド |
|---|---|---|---|
| ソニー Eマウント | フルサイズ APS-C | 小型レンズが多め サードパーティが多く、 選択肢が多い | SONY SIGMA TAMRON |
| キヤノン EFマウント | フルサイズ APS-C | 高画質レンズが有名 サードパーティが少ない | Canon SIGMA TAMRON コシナ |
| ニコン Zマウント | フルサイズ APS-C | 描写力に定評 ラインナップは少なめ | Nikon SIGMA TAMRON コシナ |
| 富士フイルム Xマウント | APS-C | APS-C専用 コンパクトなレンズ | FUJIFIMLM SIGMA TAMRON コシナ |
| マイクロ フォーサーズ | マイクロ フォーサーズ | 小型・軽量 メーカー間で互換性あり | OM SYSTEM Pamasonic SIGMA TAMRON コシナ |
サードパーティ製のレンズブランドについては下記をタップすると確認できます。
サードパーティレンズの特徴(タップして開く)
一眼カメラ初心者向けに日本企業のサードパーティレンズブランドの特徴をまとめました。
SONY Eマウントのラインナップが最も多く、次いでキャノンEFマウントが多くなります。
初心者向け サードパーティブランド
| ブランド名 | マウントの種類 | 特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| シグマ (SIGMA) | ソニーE ニコンZ キャノンEF パナソニックL など | 光学性能の追求者 純正を凌駕することもあるシャープな描写力が魅力の「Art」ラインが有名 ビルドクオリティも非常に高い。 | 詳細を見る |
| タムロン (TAMRON) | ソニーE ニコンF キャノンEF 富士フイルムX | 小型・軽量な便利ズームが多い 高倍率ズームやF2.8通しの小型大口径ズームなど利便性と画質を両立させたレンズが多い | 詳細を見る |
| コシナ (COSINA) | ソニーE ニコンZ 富士フイルムX OMマイクロ など | MFレンズの工芸品 「フォクトレンダー」「ツァイス」ブランドで、金属製の高品質なMFレンズを展開。 | 詳細を見る |



SONYは、コスパに優れたサードパーティブランドが選びやすいのもメリットですね
軽さとコンパクトさ【携帯性】
ミラーレス一眼カメラとレンズの重さは、基本的に合計1kg以下にするのがおすすめです。
カメラの他に、追加レンズや三脚、メンテナンスパーツなどを携行すると、重さがかなり増えるため、全体的なバランスを考慮して選ぶ必要があります。



ある程度の重い荷物を担げるように自分の体力を強化することもカメラを楽しむために大切になりますね
登山でカメラを持ち運ぶ方法については、下記にまとめていますので、合わせてご覧ください。
>> 一眼カメラの持ち運び方詳細(タップして移動)
防塵防滴・耐低温性能【堅牢性】
山では、突然の雨や気温の変化など過酷な環境になるため、「防塵防滴性能」と「温度耐性」が高いモデルがおすすめです。
最近では、高い耐久性を誇るマイクロフォーサーズ規格の「OM-5 Mark II」が登場して話題になっており、耐久性に不安を感じる方には特におすすめのモデルです。
一方で、フルサイズのカメラでは、高耐久モデルが少ないため、携行方法で工夫しながら使う必要があります。
>> フルサイズカメラの携行方法(タップして移動)
ボディ内手ブレ補正【撮影成功率UP】
写真撮影の3大失敗(露出、ピンボケ、手ブレ)のひとつ、手ブレを軽減してくれる「ボディ内手ブレ補正」は重要です。
三脚が使いにくい登山道や、薄暗い森の中でも手持ち撮影を強力にサポートしてくれるので、写真の失敗率が劇的に下がります。



特に初心者には強く推奨したい機能です
バッテリー性能【スタミナ】


バッテリー持ち時間は、カメラの生命線になるため、撮影可能枚数や動画撮影時間の目安は必ず確認しておくことをおすすめします。
登山で動画撮影する場合の目安は、1日の約8時間の山行で、4時間あれば満足度の高い映像を残せます。
写真は、人によって枚数が異なりますが、1日1000枚は撮影できると安心できます。
センサーサイズとバッテリー持ち時間の関係
| センサーサイズ | バッテリー持ち時間 |
|---|---|
| フルサイズ | 良い ボディが大きく、大容量バッテリーを搭載するモデルが多い |
| APS-C | 普通 ボディサイズに比例したバッテリーを搭載 |
| マイクロフォーサーズ | 短い 小型・軽量化のためにバッテリーも小さい |
登山中にバッテリー切れになっても焦らないように、予備バッテリーは最低でも1〜2個は携行してください。



長期の山行を考えるなら、モバイルバッテリーが使える「USB充電・給電」に対応しているモデルだと非常に心強いですよ
操作性【使いやすさ】


一瞬のシャッターチャンスを逃さないために、カメラの操作性は重要です。
- グリップの握りやすさ
- ファインダーの有無
- 可動式モニターの形式
- ボタン・ダイヤル位置
- ボタンのカスタマイズ性
グリップの握りやすさ


深く、指がしっかりと収まるグリップは、登山での安定した撮影の土台となります。
特に、望遠レンズを装着した際や、足場が不安定な場所では、この握りやすさが手ブレの軽減に直結します。
ファインダーの位置


日中の稜線など強い日差しの下では液晶モニターが見えにくくなるため、電子ビューファインダー(EVF)は必須です。
ファインダーを覗くことでカメラが顔に固定され、より撮影に集中できるだけでなく、体勢も安定します。
可動式モニターの形式


高山植物などの低いアングルや自撮りなどあらゆるシーンに対応するために可動式モニターも必要です。
素早く風景を撮るなら「チルト式」、自撮りや縦位置撮影もするなら「バリアングル式」がおすすめです。
ボタン・ダイヤルの位置


シャッターボタン、絞りやISO感度を変更するダイヤル類が、グリップを握った右手で自然に操作できる位置にあるかは極めて重要です。
特に、親指の位置にフォーカスを操作するジョイスティックや、AF-ONボタンがあると、ファインダーを覗いたまま素早くピントが合わせられます。
ボタンのカスタマイズ性


よく使う機能を任意のボタンに割り当てられる「カスタムボタン」の機能が充実しているほど、自分好みにカメラを最適化できます。
カスタマイズボタンがあれば、グローブをしたままでもメニュー画面を開くことなく、瞬時に設定を変更できます。
動画性能【解像度・フレームレート】
登山の記録をVlogで残したいなら、映像の質を決定づける
- 解像度
- フレームレート
- 手ぶれ補正
- マイク性能
についてもチェックが必要です。
解像度
現在の主流は4Kです。風景のディテールを美しく記録できるだけでなく、編集で映像の一部を切り取っても画質が劣化しにくいのがメリットです。
フレームレート
60p以上で撮影できると、撮影の幅が広がり、流れる雲や水の動きなどを滑らかに表現でき、映像の表現力が格段に上がります。
手ブレ補正
歩きながら安定した撮影をするためには、強力な電子手ブレ補正(アクティブモードなど)が必須です。
マイク性能
山の稜線は風が強いため、風切り音を防ぐ外部マイクはほぼ必須のため、マイク端子があるかは必ず確認が必要です。
これら8つの項目を大前提において、登山の撮影に適したミラーレス一眼を検討していきました。
>> 目次に戻る⇑
【ブランド別】一眼カメラの特徴 比較
筆者が集めた情報を下に、個人的見解として、各カメラブランドを比較・評価してみました。
カメラブランドの特徴 比較
| ブランド メーカー | SONY | Canon | OM SYSTEM 旧: OLIMPUS | Nikon | Panasonic | FUJIFILM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサー サイズ | フルサイズ | フルサイズ | マイクロフォーサーズ | フルサイズ | フルサイズ マイクロフォーサーズ | APS-C |
| 画質 【表現力】 | かなり高い | かなり高い | やや低い | かなり高い | 高い | 高い |
| レンズシステムの拡張性 【将来性】 | かなり高い | やや低い | かなり高い | 高い | 高い | 高い |
| 軽さ コンパクトさ 【携帯性】 | 高い | やや低い | かなり高い | 高い | かなり高い | かなり高い |
| 防塵防滴 耐低温性能 【堅牢性】 | やや低い | 高い | かなり高い | 高い | やや低い | 高い |
| 手ブレ補正 【撮影成功率】 | 高い | かなり高い | かなり高い | 高い | 高い | 高い |
| バッテリー性能 【スタミナ】 | 高い | やや低い | 低め | 高い | やや低い | 高い |
| 操作性 【使いやすさ】 | やや低い | かなり高い | やや低い | かなり高い | やや低い | 高い |
| 動画性能 【Vlog・記録】 | かなり高い | かなり高い | やや低い | 高い | かなり高い | 高い |
| インフルエンサー | 【登山系】 JINさん ICHIKAWAさん とよさん 【カメラ系】 Y.Ishidaさん W.Hayashiさん など多数 | 【カメラ系】 西田省三さん ゆーとびさん Y.Ishidaさん など | 【登山系】 MARiAさん | ー | ー | ー |



最終的に登山で使ってより美しい写真・映像を撮影するために、フルサイズか携帯性と堅牢性が高いモデルを選ぼうと決めました
実際に、インフルエンサーやプロカメラマンが使っているモデルも調査する中で、
- SONY:風景写真におすすめ
- Canon:人物写真に強み
- OM SYSTEM:軽量・耐久性が魅力
3つのブランドから選ぶことにしました。
>> 目次に戻る⇑
【比較】おすすめのミラーレス一眼 4選
ミラーレス一眼を選ぶにあたり、多くの登山家やインフルエンサーが使っている人気のモデルを4つ厳選して、徹底比較しました。
カメラを選ぶにあたり、
- 公式サイト・カタログのスペック確認
- WEBメディア・ブログ
- YouTube
- 店舗訪問
- 知り合いのカメラ好きに聞く
といった、情報を集めて徹底的に検討してきました。
おすすめミラーレス一眼のスペック比較
| ブランド 写真 | 登山 おすすめ度 | 特徴 | 参考価格 (税込) | ページ内 詳細へ移動 | センサーサイズ | 有効画素数 | マウント形状 | ボディ内手ブレ補正 | バッテリー性能 | 可動式モニター | 操作性 | 動画性能 | 耐久性 | 重さ |
(5.0 / 5.0) | フルサイズ 高性能ながら小型サイズ グリップが浅く操作性やや低め | 252,000円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約3300万画素 | ソニーE | 最大7.0段 | 約530枚 | バリアングル式 | グリップが小さめ ボタンが少なめ | 4K60p | 0~40℃ | 約514g | |
(4.5 / 5.0) | 信頼と安定の高機能モデル やや重たく、携帯性に欠ける | 289,438円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約3300万画素 | ソニーE | 最大5.5段 | 約520枚 | バリアングル式 | 握りやすいグリップ ボタンが豊富 | 4K60p | 0~40℃ | 約658g | |
(4.0 / 5.0) | 安定した撮影性能に強み 重ため、画素数は控えめ | 29,6989円 | 詳細を見る | フルサイズ | 約2420万画素 | キャノンEF | 最大8.0段 | 約450枚 | バリアングル式 | 握りやすいグリップ ボタンが豊富 | 4K 60p フルHD 180p | 0~40℃ | 約670g | |
OM SYSTEM OM-5 Mark II | (3.5 / 5.0) | 圧倒的な軽さと耐久性を実現 フルサイズより画質は劣る | 162,800円 | 詳細を見る | マイクロ フォーサーズ | 約2037万画素 | マイクロフォーサーズ | 最大6.5段 | 約310枚 | 3.0型2軸 可動式液晶 | グリップは小さめ ボタンが少ない | C4K:24p 4K:30p FHD:60p | -10~40℃ | 約414g |
具体的な商品レビューと私が選択した考え方をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
- SONY α7C II 【フルサイズで圧倒的に軽くてコンパクト】
- SONY α7 IV 【操作性と信頼性。正統派フルサイズの実力派】
- Canon EOS R6 Mark II【信頼の高性能オールラウンダー】
- OM SYSTEM OM-5 【機動力とタフネスの覇者】



最終的に、私は、フルサイズで圧倒的な画質性能を持ちながら、軽量・コンパクトサイズを実現している「SONY α7C II」を選びました
SONY α7C II
【フルサイズで圧倒的に軽くてコンパクト】


- フルサイズの圧倒的な高画質性能
- 高速なオートフォーカスが優秀
- 驚異的な軽さ(約514g)
- 4K60pの動画撮影も可能
- 高性能レンズが豊富にラインナップ
- グリップが浅く、やや持ちにくい
- カードスロットが一つしかない
- ファインダーの倍率が低く、少し小さく見える
- ファインダーの位置が左側に寄っている
- 4K 60p動画撮影時に画角がクロップされる
- 価格が非常に高価
- 操作ボタンが少なく、カスタマイズ性は少ない
【商品の特徴】
SONY α7C IIは、フルサイズセンサーの中でも、驚異的な小型・軽量ボディに凝縮したモデル。
ソニーEマウントは、SONYとサードパーティー製のレンズのラインナップが豊富で、選択肢が多い点も魅力的です。
SONY α7C IIのスペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約3300万画素 |
| 最高動画性能 | 4K60p |
| 重さ(バッテリー等込) | 約514g |
| ボディ内手ブレ補正 | あり(最大7.0段) |
| 防塵防滴性能 | 配慮設計 |
| 背面モニター | バリアングル式 |
SONY α7C IIのおすすめできる人、できない人をまとめてみたので参考にしてください。
- フルサイズカメラで軽量クラスを求める人
- 星空や朝焼けなどの映像に妥協したくない人
- 初めてだけど、本気でカメラを始めたい人
- 予算を最優先に考えている人
- より軽量・コンパクトなモデルを選びたい人
- 耐久性の高いモデルを求める人
- プロのカメラマンを目指したい人
【筆者の一言】
最終的に、「画質も軽さも妥協したくない」という観点で、SONY α7C IIに決めました。
一眼カメラを本気で始めるなら、画質にこだわるためにフルサイズが最適解。
カメラ本体とレンズを合わせると、かなり高価ですが、安価なモデルにしても、買い替える可能性が高いと判断しました。



実際に使い始めて、ちょうど良いサイズ感で持ち運びができているので、購入して本当に良かったです!
SONY α7 IV
【操作性と信頼性。正統派フルサイズの実力派】


- フルサイズセンサーによる卓越した高画質
- 深くて握りやすいグリップ力
- デュアルカードスロットに対応
- 視認性の高いビューファインダー
- 豊富なカスタムボタンによる高い操作性
- やや重たい
- AF性能や手ブレ補正性能がα7Ciiにやや劣る
- 4K 60p動画撮影時に画角がクロップされる
- 価格が高価
- ボタンが多くて戸惑う
【商品の特徴】
SONY α7 IVは、フルサイズミラーレスの「基準」となる、非常にバランスの取れた高性能モデルです。
SONY α7C IIと比較して、ボディは一回り大きいですが、
- しっかり握れる深いグリップ
- 高精細なファインダー
- 豊富なカスタムボタン
- デュアルカードスロット
を備えており、プロ仕様に仕上がっています。
あらゆる撮影シーンに高いレベルで応える安定感と信頼性で、プロの写真家に大人気のモデルです。
SONY α7 VIのスペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約3300万画素 |
| 最高動画性能 | 4K60p |
| 重さ(バッテリー等込) | 約658g |
| ボディ内手ブレ補正 | あり (最大5.5段) |
| 防塵防滴性能 | 配慮設計 |
| 背面モニター | バリアングル式 |
SONY α7 IVがおすすめできる人とできない人をまとめてみました。
- グリップの握りやすさや操作性を重視する人
- データバックアップが必須なプロレベルの人
- ファインダーを覗いてがっつり撮影したい人
- 1gでも装備を軽くしたい人
- 最高のAF性能や手ブレ補正を必要としない人
- カメラ初心者でシンプルな操作性を求める人
【筆者の一言】
SONY α7 IVを採用しなかった理由は、α7 Ciiより100gも重たく、やや大きく点です。
ただし、SONY α7 IVにはあるが、α7 Ciiにはない
- グリップの持ちやすさ
- ボタンの押しやすさとカスタマイズ性
- デュアルスロットルがある
- ビューファインダーが中央で見やすい
といった、多くの点でα7 Ciiより優位な点があるため最後まで迷いました。
登山では、1gでも軽くいしたいという思いがあり、今回は使いやすさよりもどこにでも持っていける軽さを重視しています。



100gの重さが気にならないくらい体力がある方なら、α7 IVはかなりおすすめのモデルですよ!
Canon EOS R6 Mark II
【信頼の高性能オールラウンダー】


- フルサイズの圧倒的な画質性能
- 業界最高クラスの手ぶれ補正最大8.0段
- 被写体検出AFが優秀
- クロップなしの4K60p動画撮影できる
- 握りやすいグリップと優れた操作性
- 登山では重ため約670g
- 価格は高め
- RFレンズのサードパーティモデルが少なめ
- バッテリー消耗は比較的早い傾向
【商品の特徴】
Canon EOS R6 Mark IIは、初代R6から正統進化を遂げ、静止画と動画の両方で極めて高い性能を発揮する、Canonのフルサイズミラーレスを代表する大人気モデルです。
風景、野生動物、星空、Vlog撮影まで、登山で撮りたいあらゆるシーンに一台で応えてくれる、まさに「オールラウンダー」のカメラです。
Canon EOS R6 Mark IIのスペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 |
| 最高動画性能 | 4K60p |
| 重さ(バッテリー等込) | 約670g |
| ボディ内手ブレ補正 | あり(最大8.0段) |
| 防塵防滴性能 | あり |
| 背面モニター | バリアングル式 |
Canon EOS R6 Mark IIが、おすすめできる人、できない人をまとめてみました。
- 風景、野生動物や人物など幅広く撮影したい人
- 写真も動画も妥協したくない人
- 軽さより性能を重視する人
- 1gでも装備を軽くしたい人
- 風景撮影がメインの人
- 予算を抑えたい人
【筆者の一言】
Canon EOS R6 Mark IIは、風景だけでなく、鳥や動物、人物撮影にも高いパフォーマンスを発揮するので魅力的です。
ただ、SONY α7C IIと比べると、
- 重さが約150gは重たくなる
- レンズのラインナップが限定的
- 使っている登山系写真家は少なめ
- 価格はやや高い
といった点から、初めて選ぶにハードルが高いと判断しました。



Canonの画像が好きな方で、重さを許容できる体力があるなら、おすすめの一台ですね
OM SYSTEM OM-5
【機動力とタフネスの覇者】


- IP53規格の高い防塵防滴・耐低温性能
- 圧倒的な小型・軽量モデル
- 強力なボディ内手ブレ補正
- 三脚なしで高解像度撮影ができる
- コンパクトな超望遠レンズが使える
- 暗所性能や高感度耐性はフルサイズ/APS-Cに劣る
- 背景を大きくぼかした表現は苦手
- メニューの構造が少し複雑
- AFの追従性能は最新の他社モデルに劣る
【商品の特徴】
OM SYSTEM OM-5 Mark-IIは、登山に求められる耐久性と軽量性を両立したマイクロフォーサーズ規格のモデルです。
過酷な環境になる登山でも、安心して撮影できるのは最大の魅力で多くの登山家に選ばれています。
「コンデジやスマホでは物足りない」けど、フルサイズほど本格的な写真を求めない方に特におすすめです。
OM SYSTEM OM-5 Mark-IIのスペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサーサイズ | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 約2037万画素 |
| 最高動画性能 | C4K60p |
| 重さ(バッテリー等込) | 約414g |
| ボディ内手ブレ補正 | あり (最大6.5段) |
| 防塵防滴性能 | IP53 (非常に高い) |
| 背面モニター | バリアングル式 |
OM SYSTEM OM-5 Mark-IIが、おすすめできる人とできない人をまとめてみました。
- 軽さを重視する人
- 機動力を重視する人
- 厳しい環境でも安心して撮影したい人
- スマホ以上の画質を求める人
- より鮮明な画質を求める人
- 星空撮影など暗所での画質を求める人
- 背景をぼかした写真を撮りたい人
【筆者の一言】
OM SYSTEM OM-5 Mark IIは、軽さを重視するなら最適解だと考えましたが、今回は写真にもこだわりたいとの思いから採用しませんでした。



マイクロフォーサーズ規格は、賛否が別れるところですが、スマホでは撮れない味のある写真や動画を撮影したいならおすすめのモデルですよ
>> 目次に戻る⇑
レンズの選び方とおすすめモデル 3選
ミラーレス一眼で撮影するためには、カメラのレンズは必須です。
レンズを選びのポイントは、
- 撮影したいもの・景色
- マウントの形状
- レンズの種類・焦点距離
- 簡易防滴構造
- 開放F値
- 重さとサイズ感
- 描写性能
- AF(オートフォーカス)性能
- レンズ内手ぶれ補正
- 操作性
を考慮して総合的に選びます。
今回は、SONY製カメラのEマウントから、初心者向けに登山で人気のおすすめレンズを3つ厳選しました。
おすすめレンズ 3選
| メーカー 商品名 | Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD | Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | SONY FE 24-105mm F4 G OSS |
|---|---|---|---|
| 写真 | |||
| レンズの種類 | 高倍率ズーム | 高倍率ズーム | 標準ズーム |
| ポイント | 広角から望遠までカバー F2.8でボケ感が出せる やや広角は狭い印象 | 20mm広角端がすごい 高倍率ズームもカバー F3.5で星空は厳しめ | 広角から中距離望遠まで 景色撮影におすすめ24mm広角端 望遠は弱い |
| 焦点距離 | 28-200mm | 20-200mm | 24-105mm |
| 開放F値 | 2.8-5.6 | 3.5-6.3 | 4 |
| レンズ内 手ブレ補正 | なし | あり | あり |
| 重さ | 575g | 540g | 663g |
| サイズ | Φ74 × 117mm | Φ77×118mm | Φ83×113mm |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| 参考価格(税込) セール時価格 | 74,131円 | 130,000円 | 145,800円 |
| Amazon | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |



最初のレンズはものすごく迷いますが、焦点距離の広さと価格がリーズナブルなTamron 28-200mmを選びました
様々な距離を1本で撮影できて、ボケ感のある写真や動画を撮影しやすいので、かなり使いやすいレンズです。
ただ、実際に使い始めると、28mmの広角域で景色を撮影すると、狭さを感じることがあるため、広角端24mmのレンズを検討しています。
>> 目次に戻る⇑
失敗しないためにレンタルがおすすめ



数十万円するミラーレス一眼をいきなり購入するのはかなり不安⋯



カメラレンタルサービスを使えば、失敗するリスクがかなり下がりますよ!
高額のミラーレス一眼とレンズを購入すると最低でも30万円近くしますが、カメラの「レンタルサービス」なら約3万円で1ヶ月間みっちり借りられます。
大手のカメラレンタルサービスで、価格比較表にまとめたので、参考にしてください。
レンタルサービス5社比較
| ロゴ サービス名 | モノカリ | ||||
| 利用可能モデル | SONY α7C II FE 50mm | SONY α7 III FE 28-75mm | SONY α6400 E18-135mm | SONY α7 III FE 28-75mm | SONY α7R III FE 24-70mm |
| 短期レンタル 料金(税込) | 1泊2日 12,562円 | 3泊4日 12,420円 | 4泊5日 9,990円 | 3泊4日 23,300円 | 3泊4日 25,200円 |
| 延長料金(税込) ※1日当たり | ー | 1,480円 | 400円 | 2,500円 | 2,520円 |
| 1ヵ月レンタル 料金(税込) | 28,930円 ※送料込み | 25,800円 ※3か月~ | ー | ー | ー |
| ポイント | 月額利用がお得 カメラ交換し放題 | 短期利用がお得 | 旧モデルが多い | SDカードがついてくる | レンズセット品 が限定的 |
| 本人確認 | あり 電話で確認 +追加書類 | あり マイナンバー登録 | なし | なし | 必要 書類確認 +本人クレジット |
| 保険料 | レンタル料に含む | レンタル料に含む | レンタル料に含む | レンタル料に含む | レンタル料金の10%で保険加入可 |
| 補償対象 免責額 | 上限5000円 | 上限2000円 | 上限5000円 | 上限2000円 | 保険必要 |
| 保障対象外の対応 | 補償対象外の損害は、全額実費負担 | 保証対象外の損害は、全額実費負担 | 補償対象外の損害は、全額実費負担 | 補償対象外の損害は、全額実費負担 | 補償対象外の損害は、全額実費負担 |
| SDカード付属 | なし | 64GB 返却不要 | 32GB 返却必要 | 64GB 返却不要 | 64GB 返却必要 |
| 付属品セット | カメラ レンズ類 バッテリー ケーブル 充電台 ポーチなど | カメラ レンズ類 バッテリー ケーブル など | カメラ レンズ類 バッテリー アダプター SDカード32GB など | カメラ レンズ類 バッテリー アダプター SDカード64GB など | カメラ レンズ類 バッテリー×2 アダプター SDカード64GB など |
| 公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
価格は送料込みを記載(一部地域除く場合あり)
本人確認は少し手間に感じるかもしれませんが、高価なカメラの盗難リスクを考慮すれば企業側の姿勢は理解できます。



いきなり30万円以上するカメラを購入して、失敗したくない方はレンタルサービスで試してみるのもおすすめですね
\月額利用でみっちり使う!/
電話の本人確認はとても丁寧
\短期利用で手応えを感じる!/
本人確認はマイナンバー登録のみ
>> 目次に戻る⇑
登山の撮影におすすめのアクセサリー 5選
カメラ本体とレンズ以外に、登山でミラーレス一眼を使うために必要なアクセサリーを5つ厳選しました。
予備バッテリーと充電台


ミラーレス一眼カメラは消費電力が大きいため、最低でも1つ、できれば2つの予備バッテリーを持つようにするのがおすすめです。
バッテリー充電を効率的にするために、複数のバッテリーを装着できる充電台も合わせて準備してみてください。
高価なカメラを扱うため、故障や発火リスクを考慮すれば純正品のバッテリーがおすすめですよ



ちなみに、私は充電台だけサードパーティ製を使っています
レンズ保護ガード


登山では、砂塵や岩場にレンズをこすって傷つけるリスクが高いため、透明なガラスフィルターの装着は必須です。
レンズ保護ガードは、価格が数千円から数万円するものもあり、高価なレンズほど強度や光の透過率が高いものが多くなります。



私は、口コミなどを参考にしてHAKUBAのPROタイプを選びましたが、変な光も入らず、安心して撮影を楽しめていますよ!
1kg以下の三脚とマウント


ご来光や夕焼け、満点の星空など、光量が少ない状況でブレのないクリアな写真を撮るためには三脚は必須です。
登山用には、軽さと収納時のコンパクトさを追求したカーボンファイバー製の三脚が人気ですが、かなり高価なため、始めはアルミ製の三脚を選びました。
重さは1.2kgですが、長さ・収納性・安定性・使いやすさのバランスがかなり高いので満足度は高いです。
【雲台用のワンタッチ着脱マウント】
三脚と合わせて持っておきたいのが、カメラと雲台をワンタッチで着脱できるマウントです。


通常は、ネジを回して着脱しますが、ワンタッチで着脱できるマウントがあれば、撮影時のストレスが大幅に軽減できます。
ブロアー と レンズペン


レンズに付着したホコリや汚れをスムーズに取り除けるメンテナンスアイテムです。
ホコリは傷の原因になるため、ブロアーの強い風で吹き飛ばし、それでも取れない汚れや指紋をレンズクロスで優しく拭き取るのが基本です。
特に、HAKUBAのレンズペンは、ブラシとクロスが一体のペン型クリーナーで、持ち運びがとても便利です。





カメラポーチにも収まりやすく、非常に使いやすいのでおすすめです
登山での持ち運び方 アクセサリー 3選


高価で精密なカメラを安全かつ快適に持ち運ぶ方法として、
- カメラポーチ
- カメラクリップ
- ショルダーハーネス
が代表的です。
安全性・速写性・携行性の3つの観点で比較しました。
カメラポーチ


最もバランスが優れているのが、ザックのショルダーハーネスやウエストベルトに取り付けられる、小型のカメラ用ポーチです。
カメラクリップのように剥き出しの状態ではないため、岩や木にぶつけるリスクを軽減でき、クッション性が高く、多少の雨なら弾いてくれる素材のものを選ぶのがおすすめです。
カメラポーチの比較するポイントは、
- サイズ感:カメラとレンズが入るか
- 収納性:カメラ以外のアクセサリーが入るか
- 防水性:防水性は高いか
- クッション性:カメラを保護できるか
- 持ち運びやすさ:ザックへ固定しやすいか
の観点から選びました。
カメラポーチの比較
| ブランド | サイズ感 | 収納性 | 防水性 | クッション性 | 持ち運びやすさ | 参考価格(税込) | Amazon |
  PaaGo WORKS Focus L | カメラ +ズームレンズ +小さめレンズ | 両サイド 前面ポケット | 高め 撥水生地 | 普通 | チェスト ショルダー バッグ | 14,850円 | 詳細を見る |
  ザ・ノーズ・フェース EXカメラバッグ | カメラ +ズームレンズ | 前面ポケット | 低め | 普通 | ショルダー バッグ | 9,000円 | 詳細を見る |
  mont-bell カメラバッグ | カメラ +ズームレンズ +標準レンズ | 両サイド 前面ポケット | 高め | 普通 | ショルダー バッグ | 8,800円 | 詳細を見る |
  HAKUBA カメラバッグ | カメラ +ズームレンズ | 両サイド 前面ポケット | 普通 レインカバー 付属 | 普通 | ショルダー | 6,280円 | 詳細を見る |
  Coleman カメラホルスタ | カメラ +ズームレンズ | 両サイド 前面ポケット | 低め | 普通 | ショルダー バッグ | 3,993円 | 詳細を見る |
  HIKEMAN カメラケース | カメラ +ズームレンズ | 両サイド 前面ポケット | 高め 撥水生地 | 普通 | チェスト ショルダー バッグ | 4,990円 | 詳細を見る |



PaaGo WORKS Focus Lは、痒いところまで手が届くデザイン性の高さから選びました
SONY α7C IIともう一つレンズが入り、サイドの収縮性の高い生地部やポケットにメンテナンスキットやバッテリー、小物を収納できます。
バックパック用カメラホルスター


カメラクリップは、多くの登山家が愛用しており、ザックに固定することでカメラの重さが両肩に分散でき、速射性に優れた携行スタイルです。
ただし、急な岩場や鎖場でも、カメラを気にせず安全に通過できるため、もはや登山の標準装備と言っても過言ではありません。
ショルダーストラップ


カメラをストラップで肩にかけて、レインカバーを装着するスタイルで携行性と速射性に優れていますが、安全性に課題が残ります。
特に、肘の下部分に当たって、移動時にはややストレスに感じる方もいるため、登山ではあまりおすすめでいません。



街で撮影する方には、ショルダーストラップで携行する方をよく見かけますよね
>> 目次に戻る⇑
保管・メンテナンス用アクセサリー 3選
大切な一眼カメラを大切に使うために、メンテナンスと適切な保管には妥協が許されないポイントです。
カメラを始めるなら、
を揃えておくのがおすすめです。
防湿庫(ドライボックス)


カメラとレンズにとって最大の敵は「湿気」を減らすために、保管の際は防湿庫が必要です。
湿度が高い状態で長期間保管すると、レンズ内部にカビが発生し、修理に高額な費用がかかることもあります。
電動で常時湿度を管理してくれる本格的なタイプもありますが、まずは密閉できるプラスチックケースに乾燥剤を入れる、簡易的な「ドライボックス」から始めるのがおすすめです。



HAKUBAから手頃なモデルが出ているので、レンズやカメラの数で選んでみてください
強力乾燥剤(防カビ剤配合)


ドライボックス内部の湿度を一定に保つために必要なアイテムが、乾燥剤です。
ボックスの容量と乾燥剤の数で、湿度を適切に管理してくれるので、安心して使えます。
ただし、電気式のドライボックスではないため、乾燥剤の交換時期は約8ヶ月に1回必要なので、スマホのスケジュールに登録しておくことがおすすめです。



スペースも取るので、今は電動ではないドライボックスを使用していますが、いずれは電動式もほしいですね
クリーニングキット


カメラボディやレンズに付着した汚れや砂埃をきれいにするクリーニングキットは欠かせないアクセサリーです。
ホコリを吹き飛ばすブロアー】
レンズやボディ表面の大きなホコリを、傷がつかないようにブロアーの風で吹き飛ばします。
指紋や皮脂を拭き取る【レンズペン】
ブロアーやブラシで取れないレンズ表面に残った指紋や皮脂などの油汚れを取り除くために、レンズペンは非常に使いやすいです。
レンズペンの魅力
- 軽量・コンパクトで収納性が高い
- 汚れをしっかり取れる
- 予備パーツもついてコスパがいい



思いもよらず、レンズが汚れるシーンは多々あるため、撮影後に影が入るような失敗をしないためにも撮影前のレンズの確認は必須で行ってくださいね
>> 目次に戻る⇑
お気に入りのカメラで新しい表現を追求してください!
登山向け一眼カメラを選びで失敗しないために、
- 画質とセンサーサイズ【表現力】
- レンズシステムの拡張性【将来性】
- 軽さとコンパクトさ【携帯性】
- 防塵防滴・耐低温性能【堅牢性】
- ボディ内手ブレ補正【撮影成功率】
- バッテリー性能【スタミナ】
- 操作性【使いやすさ】
- 動画性能【Vlog・記録】
のポイントは必ず抑えておくのがおすすめです。



結論、登山で最もおすすめできるフルサイズカメラは、SONY α7C IIでした。
- フルサイズカメラで軽量クラスを求める人
- 星空や朝焼けなどの映像に妥協したくない人
- 初めてでも本気でカメラを始めたい人
- 予算を最優先に考えている人
- より軽量・コンパクトなモデルを選びたい人
- 耐久性の高いモデルを求める人
- プロのカメラマンを目指したい人
>> おすすめカメラ比較一覧(タップして移動)
画質も欲しいけど、軽量性と耐久性を求める方にはOM もおすすめです。
眼の前に広がる絶景をより鮮明に記録できる一眼カメラを手に入れて、一生の思い出を残してみてください!





















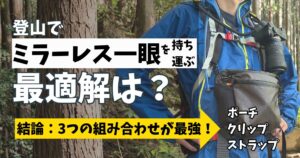

コメント